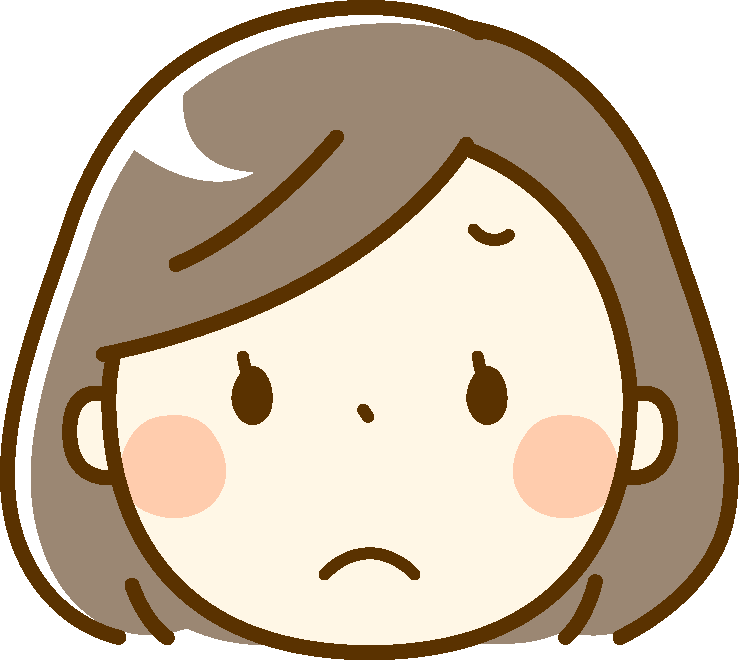
雨の日の保育園送迎、
ほんっとうに大変ですよね…!
傘はさせないし、子どもは抱っこでぐずるし、ベビーカーは濡れるしで、朝からヘトヘト。
しかも保育園の荷物は多いし、自分もびしょ濡れで出勤…なんて、共働き家庭にとってはまさに試練の日☔
この記事では、「抱っこ紐」と「ベビーカー」それぞれの雨の日対策を、
先輩ママたちの実例や保育士さんのリアルな声とともにご紹介します。
実際に使ってよかった便利グッズや、登園後のケア、ママ自身の服装の工夫まで、
明日からの登園がちょっとラクになるヒントをたっぷり詰め込みました😊
「うちも明日、これでやってみようかな」と思える内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
雨の日の保育園送迎、まずはこれが基本ルール!
抱っこ紐?ベビーカー?どちらが正解かは、実は「家庭の状況」と「天気の強さ」で変わってきます。
まずはみんながどんな手段で登園しているのか、そして選び方のポイントを押さえておきましょう。
抱っこ紐とベビーカー、雨の日はどちらが安全?
結論から言うと、小雨の日は抱っこ紐、大雨・風が強い日はベビーカーが便利なことが多いです。
抱っこ紐は両手が空くので歩きやすく、サッと移動したいときに便利。一方で、荷物が多い日や遠距離通園の場合は、カバー付きベビーカーが安全で実用的です。
また、子どもが活発になってきた1歳半以降は、暴れて足元が危ないことも。
月齢・性格・天候に合わせた選択をするのがコツです。
送迎手段の選び方とタイプ別のメリット・注意点
▼抱っこ紐派のメリット
・階段や狭い道でもスムーズに移動できる
・通園途中で泣いたときも抱っこで安心させやすい
・傘をささなくてもポンチョでカバーしやすい
▼抱っこ紐派の注意点
・ママ自身がびしょ濡れになりやすい(傘が持ちにくい)
・荷物とのバランスが悪くなると転倒のリスクが
▼ベビーカー派のメリット
・荷物が多い日もラクに運べる
・レインカバーで全体をしっかりガードできる
▼ベビーカー派の注意点
・地面からの跳ね返りや水たまりで足元が濡れやすい
・混雑した通園路では移動が大変に感じることも
先輩ママのリアル体験「こうすればスムーズだった!」
「うちはレインカバー+抱っこ紐を使い分け!」

朝から土砂降り…という日はベビーカー+全体カバーで登園。
小雨や途中で止みそうな日は、レインポンチョと抱っこ紐で時短登園に切り替えています。(2歳女の子ママ)
「ベビーカーの荷物に着替えを多めにIN!」
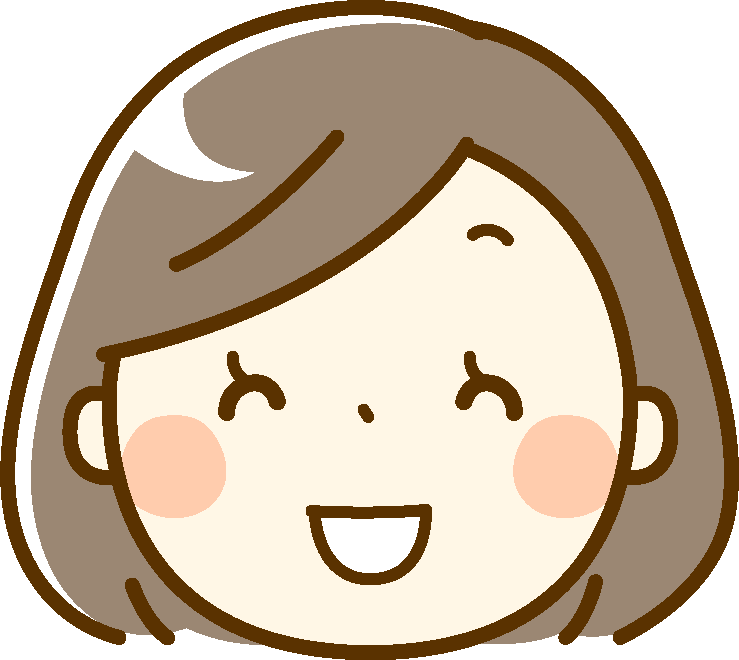
思ったより濡れてしまうことがあるので、念のため上下の着替えと靴下もベビーカーに常備しています。
着替え用の防水バッグがあると安心です。(1歳半男の子ママ)
抱っこ紐で雨の日登園するときのコツ【おすすめスタイル実例あり】

抱っこ紐での登園は、身軽で便利な反面、雨の日には濡れたり手がふさがったりと意外な落とし穴も…。
ここでは、先輩ママたちが実践している“濡れにくくて快適”なスタイルと、おすすめグッズをご紹介します☔
親子で濡れにくい装備とは?ポンチョ&服装の工夫
レインポンチョ(親子兼用タイプ)は、抱っこした状態でサッとかぶれるのでとても便利!
前開きでファスナーが大きく開くタイプなら、子どもが動いても着脱しやすく、汗をかきにくいのもポイントです。
また、親子ともに「濡れてもOKな服装」を心がけるだけでも、心のゆとりが違ってきます。
速乾素材のTシャツ、レギンス、撥水加工のアウターなどを選ぶと、保育園到着後の着替えの手間も減らせますよ。
傘なし・片手送りのためのテクニックまとめ
両手がふさがって傘がさせない場合は、撥水パーカー+つば広のレインハットが人気です。
リュックの上から着られる大きめパーカーは、荷物ごと雨をガードできるので時短にもなります。
その他にも、防水リュックカバーやビニール付きの帽子</strongなど、ちょっとした工夫で両手が空くスタイルを実現しているママも多いです。
実際に使っているおすすめレイングッズ(なおみさん談)
・親子兼用レインポンチョ(通気性あり)
軽くて持ち運びもラク。撥水性が高くてムレにくいのがポイント。
うちはベビーカーの日も、抱っこの日もこれ1枚あれば対応できるので重宝しています♪
・レインハット+防水パーカー
傘がさせないときは、頭と背中が守られる組み合わせが安心。帽子はあご紐付きで風にも強いものを選んでいます。
・防水リュックカバー
保育園グッズやお着替えセットはリュックにまとめているので、カバーをつけておくだけで濡れずに安心です。
どれも「登園時のストレスを減らす」視点で選んでいるので、雨の日が少し楽しみになるくらい快適になりました☂️
ベビーカー送迎の雨対策|失敗しないレインカバー選びと使い方

雨の日にベビーカーを使う場合、レインカバーの有無で快適さが大きく変わります。
でも、実は「買ってみたけど使いづらかった…」という声も多数。ここでは、失敗しない選び方と、実際に役立つ使い方のコツをご紹介します。
カバーの選び方と取り付けの注意点
レインカバーを選ぶときは、ベビーカーの“形状と開閉方法”に合っているかが最重要ポイント。
特に注意したいのは以下の3点です:
- ベビーカーにフィットするサイズ感か
- 着脱が簡単でサッと掛けられるか(朝は時間が勝負!)
- 通気性・視界(子どもの顔が見えるか)
透明窓付きで前が開けられるタイプは、乗せ降ろしやおやつタイムにも便利。
背面メッシュや空気穴があるとムレ対策にも◎です。
雨の日でも荷物を濡らさないコツ
ベビーカー下の荷物入れ、実はレインカバーでは守れないエリアという落とし穴も…。
そんなときは、荷物をジッパー付き防水バッグやビニール袋に入れておくと安心です。
また、ベビーカーフックに吊るすタイプの防水トートも人気。
サッと外せて、玄関先で保育士さんに渡すときもスムーズです。
帰宅後のケアまでが“ひとまとめ”で時短になる!
雨の中の登園後、帰宅してからのケアが地味に大変…。
そんなときは玄関先にタオルと防水シートをスタンバイしておくと、ベビーカーをそのまま置けて、床が濡れません。
レインカバーは、使用後すぐにタオルで拭いて干すor洗濯ネットに入れて洗濯機へ。
ポリエステル素材ならすぐ乾くので、次の日も使いやすいですよ。
保育士さんの本音「雨の日はこうしてくれると本当に助かります」
保育園に着くまでで精一杯…そんな雨の日こそ、ちょっとした工夫で先生たちの負担もグッと減らせるんです。
保育士さんが実際に「これ、してくれると本当に助かる!」と感じているポイントを集めました。
荷物・服装・声かけ…意外とありがたい工夫とは?
・荷物はひとまとめにしてビニール袋へ
雨で濡れた袋や着替えをまとめて1袋にしておくだけで、先生がスムーズに整理できます。
中が見える半透明の袋やジッパー付きだと、より安心。
・子どもが自分で脱げるレインコートや長靴
着脱しやすい服や長靴だと、保育室での対応がスピーディ。
マジックテープ式のレインブーツや、前開きレインコートは特に好評です。
・朝の「ひと声」が大きな助けに
「ズボンが濡れてます」「着替え入れてます」「風邪気味で…」など、一言そえるだけで先生は状況を把握しやすくなります。
混雑しない登園時間・動線のヒント
雨の日の玄関やロッカー周りは、普段以上に混雑します。
混み合う時間帯を少し避けて登園するだけで、スムーズな引き渡しができることも。
また、子どもが靴を脱ぐタイミングや荷物の受け渡しがしやすいよう、
ママ・パパの立ち位置や動線をちょっと工夫するだけでも、現場のバタバタ感が減ります。
子どもが笑顔でバイバイできるコツも保育士目線で
雨の日は気分が沈みがちで、子どもが泣いて離れたがらないことも…。
でも「ママが笑顔でバイバイ」するだけで、子どもが落ち着くことが多いそうです。
玄関でしっかりギュッと抱きしめて、「先生と遊んで待っててね」など
前向きな言葉かけをすると、保育士さんが引き継ぎやすくなり、子どもも安心しやすくなりますよ。
雨の日登園が楽になる!おすすめグッズと選び方ガイド
「何を使えば少しでも快適になるの?」と悩むママ・パパのために、
雨の日送迎に役立つ定番&人気グッズをピックアップしました!
実際に使って良かったものを中心に、選び方のポイントもご紹介します☔
抱っこ紐派に人気のポンチョ・ケープ・シューズカバー
・親子兼用のレインポンチョ
抱っこしたままサッとかぶれて、全体をすっぽり覆えるタイプ。
前開きでメッシュ入りのものだとムレにくく、夏場でも快適です。
・防水抱っこ紐ケープ
風が強い日や気温の低い時期は、防水・防寒が両立できるケープが便利。
スナップボタンやゴム付きで、動いてもズレにくいタイプが◎。
・レインシューズカバー(大人用)
普段のスニーカーに被せるだけで足元の不快感を防げるアイテム。
登園後に脱げば、会社に行くときの靴も濡れずに済みます。
ベビーカー派に支持される軽量カバー・傘スタンド
・フルカバー型レインカバー(透明窓つき)
前面の開閉がしやすいものは、乗せ降ろしや子どもとのやりとりにも便利。
通気性や視界の良さ、UVカット機能もあるとより安心です。
・ベビーカーに取り付けられる傘スタンド
両手がふさがらず、親子ともに濡れにくくなる便利グッズ。
ただし、風が強い日は転倒リスクもあるので注意が必要です。
ママ自身のレインコート・靴・リュック選びのポイント
・リュック対応レインコート
背中にマチがあるタイプを選ぶと、荷物を背負ったままでも快適!
足元までカバーできるロング丈だと、ズボンの濡れも防げます。
・滑りにくいレインブーツ
子どもを抱っこしたまま歩くことも考えて、グリップ力のあるソールを。
ショートブーツタイプなら動きやすく、着脱もラクちんです。
・防水リュックカバー
保育園の荷物が濡れる心配を減らせる優秀アイテム。
使わないときは折りたたんで収納できる軽量タイプが人気です。
まとめ|雨の日登園がちょっと楽になる5つのヒント
雨の日の登園は、ママ・パパにとって本当に試練のひととき。
でも、ちょっとした工夫や便利グッズの力を借りるだけで、気持ちにも時間にもゆとりが生まれます。
ここまでご紹介した内容を、改めて「明日からできる5つのヒント」としてまとめました☔
- ① 抱っこ紐 or ベビーカー、天気に合わせて無理なく選ぶ
小雨の日は抱っこ、大雨・風が強い日はベビーカーが安心◎ - ② 前日準備で“朝の慌て”を最小限に
レインカバーや着替え、荷物のまとめは前日の夜がベスト! - ③ 服装と荷物は「濡れてもいい前提」で考える
撥水素材・速乾生地・防水カバーがあると気がラクになります。 - ④ 保育士さんとの連携でスムーズ登園に
雨の日は一声そえるだけで、先生との信頼関係もUPします。 - ⑤ 「完璧じゃなくていい」気持ちのゆとりを大切に
多少濡れても大丈夫♪ 無理せず、自分にも優しくいきましょう。
大切なのは「がんばりすぎないこと」。
今日よりちょっと楽になる“自分なりの工夫”を、少しずつ見つけていきましょうね😊
☔ 雨の日登園の準備、これでバッチリ!
【完全版】梅雨の登園準備ガイド
全記事をまとめてチェック!「うちの子に合う」雨対策がきっと見つかる♪

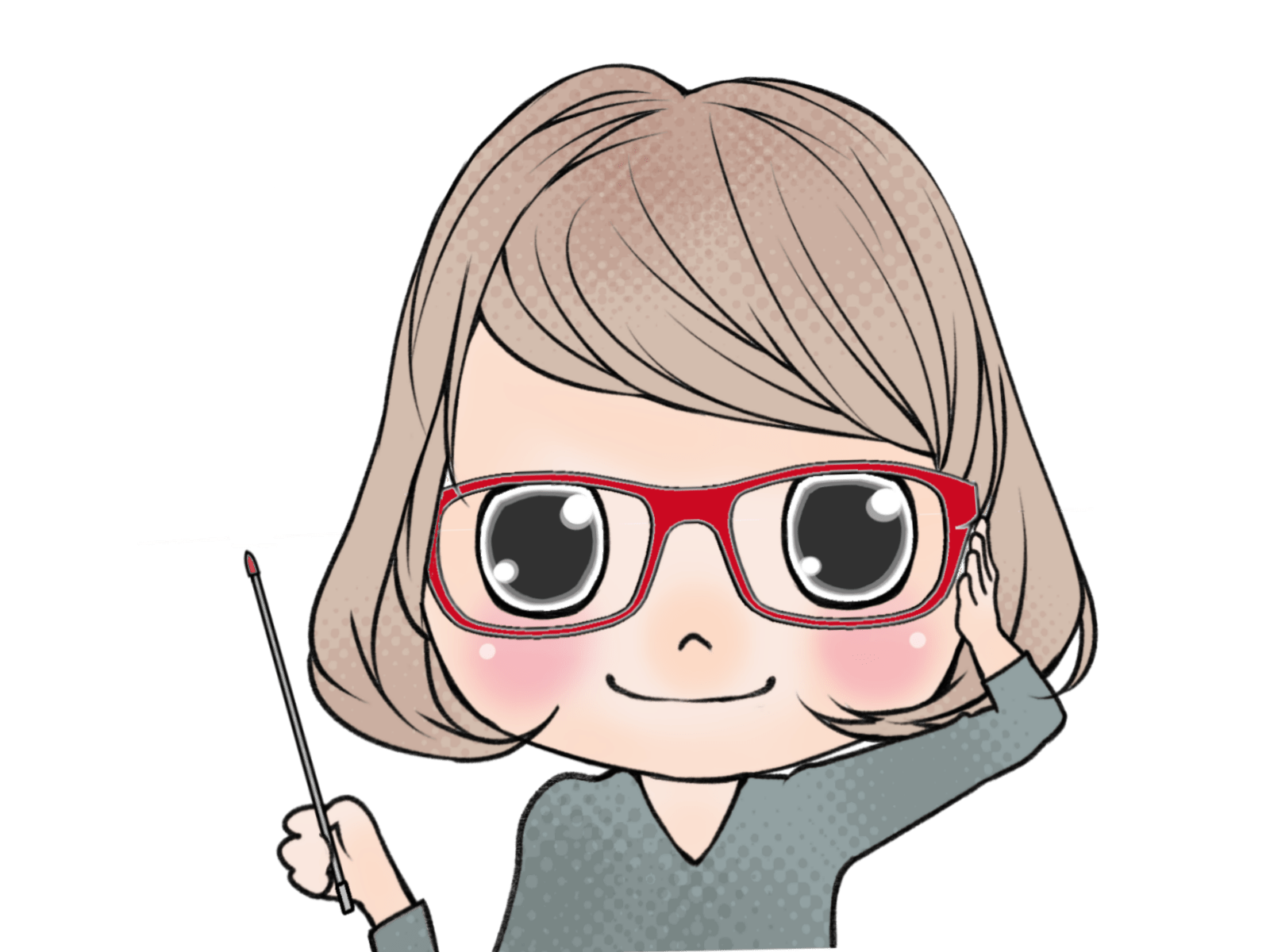
保育園ママの「雨の日どうする?」に寄り添う、7記事のまとめ特集です。気になるテーマを選んでチェックしてみてくださいね♪
レインコートはいつから?
保育園児向けのレインコートの選び方と、年齢別おすすめ商品を紹介!

抱っこ紐・ベビーカー送迎どうする?
雨の日の移動手段、みんなはどうしてる?実例と便利グッズを紹介します。

保育園で使える長靴とは?
転ばない・蒸れない・はきやすい!園児向け長靴の選び方とおすすめタイプ。

濡れた靴どうする?
登園前に焦らない!早く乾かすコツと消臭・防カビ対策まで徹底ガイド。

雨の日の保育園コーデ
濡れにくく乾きやすい服の選び方と、おすすめの着替え枚数も紹介!

リュックカバーって必要?
実は使ってない人も多い?みんなの対策・代用品・おすすめアイデアまとめ。











コメントを投稿するにはログインしてください。