「朝なかなか起きられない」「日中ぼんやりして宿題が進まない」「つい夜更かししてしまう」――。
小学生の睡眠不足や生活リズムの乱れは、学年が上がるほど目立ちやすくなります。
このままでは「集中力・成績への影響が心配」「毎晩の声かけがつらい」と感じる親御さんも多いはず。
でも、今日からできる小さな工夫で睡眠リズムは必ず整え直せます。
この記事では、まず結論(基本の3つ)を先にお伝えし、続いて
年齢別の睡眠時間の目安、睡眠不足が与える影響、チェックリスト、原因別の改善方法、親の声かけと仕組み化、リセット術の順に解説します。
関連記事も合わせて参考にしてください:
・小学生の生活習慣が乱れる原因と整え方
先に結論|小学生の睡眠不足を改善する基本はこの3つ
- 起床・就寝は「10〜15分ずつ前倒し」×3日(無理なくリズムを戻す)
- 21時以降は画面オフ+入浴→読書→就寝の夜ルーティン固定
- 朝の日光+たんぱく質の朝食で体内時計を同調
「うちの子は睡眠不足かも?」をすぐ判断できるよう、チェックリストも用意しました。
次のセクションで、まずはわが子の状態を一緒に確認していきましょう。
これで判定|小学生の睡眠不足チェックリスト(5項目)

「睡眠不足かもしれない」と感じても、実際どのくらい不足しているのか判断しにくいものです。
以下のチェックリストで、わが子の状態を確認してみましょう。
- 朝、起きるのに30分以上かかる/起きても不機嫌が続く
- 日中にあくびが多い、授業中にぼんやりする
- 宿題や作業中に集中力が続かない
- 週末は平日より2時間以上寝坊している(=生活リズムがずれているサイン)
- 夜になるとイライラや情緒不安定な様子が出る
2〜3項目以上あてはまる場合は、すでに生活リズムの乱れが始まっているかもしれません。
次の章では、まず「小学生に必要な睡眠時間の目安」を確認して、
「わが子は足りているのか?」を見ていきましょう。
年齢別の目安|小学生の睡眠時間は何時間が標準?
小学生に必要な睡眠時間は、年齢によって少しずつ異なります。
アメリカ睡眠財団や日本小児科学会の推奨値を参考にすると、以下が目安となります。
- 低学年(1〜3年生):9.5〜10時間
- 中学年(4年生):約9時間
- 高学年(5〜6年生):8.5〜9時間
例えば夜9時に就寝した場合、低学年なら翌朝7時前後、高学年でも6時半頃まで眠るのが理想です。
この目安より1時間以上短い日が続くと、日中の集中力や体調に影響が出やすくなります。
週末の「寝だめ」に注意
平日は早起きなのに、週末は2時間以上遅くまで寝る――これを「社会的時差」と呼びます。
体内時計がずれて月曜日に朝起きられなくなる原因になるため、
週末も±1時間以内の起床・就寝を心がけるとスムーズに生活リズムを保てます。
続いては、睡眠不足が子どもの学習や健康にどんな影響を及ぼすのかを見ていきましょう。
ここに出る影響|小学生の睡眠不足が学習・健康に及ぼす結果
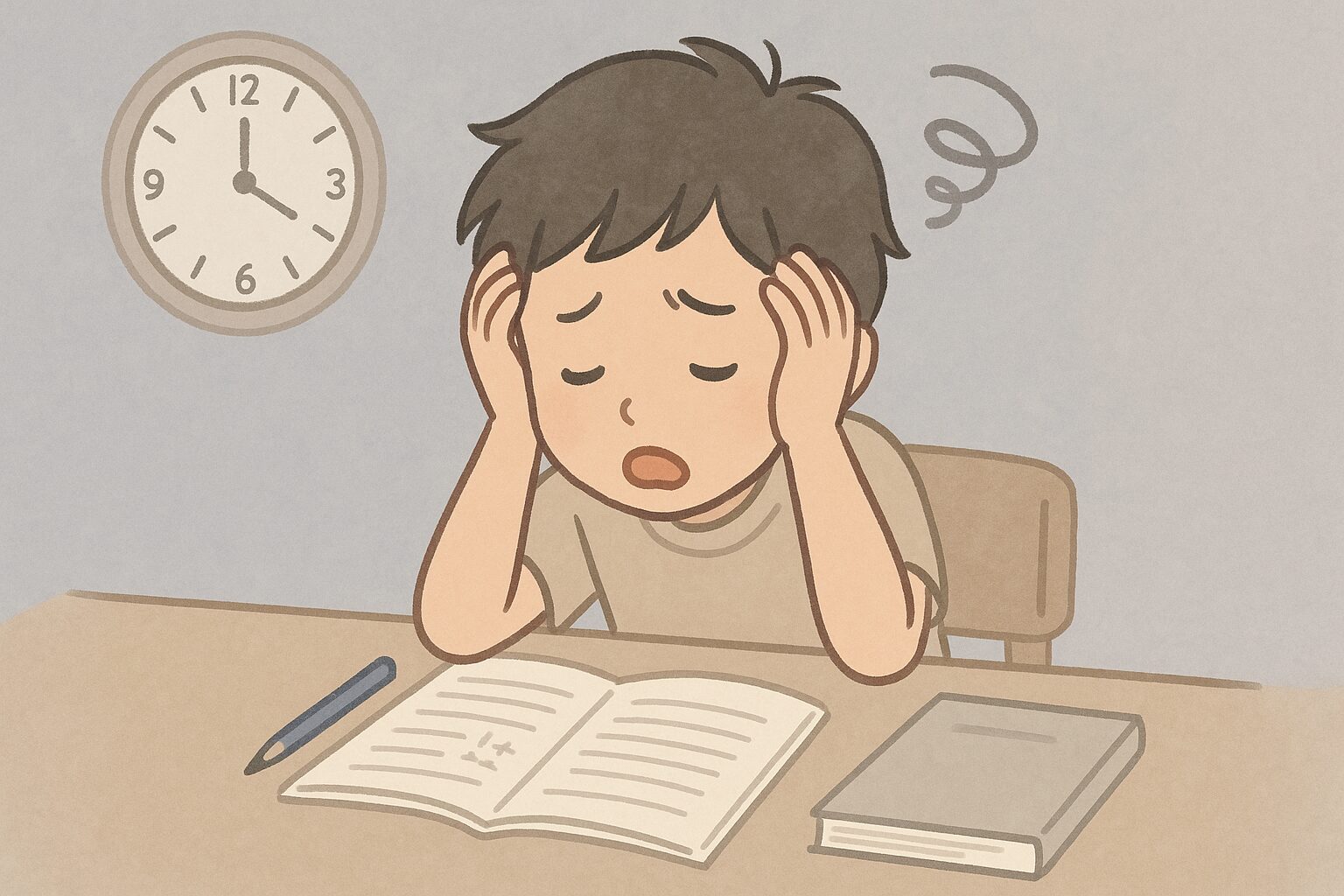
睡眠不足は「朝がつらい」だけでなく、学習・健康・心の安定にまで影響します。
ここでは、具体的にどんな変化が起こるのかを整理しました。
集中力・記憶力が落ちて「成績」に影響
睡眠中は記憶の整理と定着が行われます。
睡眠不足が続くと、授業中の集中力が途切れやすくなり、暗記や計算のスピードにも影響が出ます。
「勉強しているのに成績が上がらない」と感じるとき、実は睡眠不足が原因ということも少なくありません。
情緒不安定・イライラ・朝起きられないが増える
寝不足は自律神経のバランスを乱し、イライラや不機嫌の原因になります。
「朝なかなか起きられない」と感じるときは、朝の支度をスムーズにする工夫も参考になります。
成長ホルモンの分泌が減り、発育・免疫に影響
子どもの成長ホルモンは深い眠りのときに多く分泌されます。
睡眠が足りないと発育の妨げになるだけでなく、免疫力が下がり風邪をひきやすくなることも。
「よく体調を崩す」「背が伸びにくい」と感じるときは、睡眠の質や時間も見直す必要があります。

このように、睡眠不足は学習面・感情面・身体の発育にまで直結します。
次の章では、わが子が睡眠不足かどうかをセルフチェックできるリストを見ていきましょう。
原因別の改善方法|朝起きられない・夜更かしをこう直す

「睡眠不足を改善したい」と思っても、原因によって対策は異なります。
ここでは代表的な3つのケースごとに、すぐ試せる改善方法をまとめました。
朝起きられないときの対策|就寝逆算+朝のルーティン
朝起きられない原因の多くは、寝る時間が遅いこと。
まずは「起きたい時間から逆算」して就寝時刻を設定しましょう。
例えば朝7時に起きたいなら、21時〜22時には眠れるように準備を進めるのが理想です。
また、朝はカーテンを開けて日光を浴びる+たんぱく質のある朝ごはんで体を起こすルーティンをつくると効果的です。
「起きたい時間から逆算して就寝時間を決める」ことが第一歩です。
詳しくは 朝の支度と忘れ物対策の記事 もチェックしてみてください。
夜更かしの直し方|21時画面オフ+入浴→読書→就寝
寝る直前までゲームやスマホをしていると、脳が興奮して寝つきにくくなります。
21時以降は画面オフを合図にし、
「入浴 → 歯みがき → 読書 → 就寝」といった毎晩同じ流れを固定しましょう。
子どもが安心して眠れる“おやすみルーティン”を習慣化するのがポイントです。
夜の工夫については 夜更かし対策の記事 で詳しく紹介しています。
塾や習い事で寝るのが遅い日の対応|翌朝10分スライド
塾や習い事でどうしても就寝が遅くなる日もあります。
そんな日は翌朝の起床を10〜15分だけ遅らせるなど、柔軟に調整することも大切です。
完全に帳尻を合わせようとせず、「続けて不足しないこと」を意識するだけでもリズムは安定しやすくなります。
続いては、親ができる声かけや仕組みづくりを具体的に見ていきましょう。
親ができる声かけと仕組み化(例文つき)
「早く寝なさい!」を繰り返しても、子どもはなかなか素直に動いてくれません。
大切なのは声かけの工夫と仕組みづくりで、子どもが自分から行動しやすい環境をつくることです。
実況型・選択型・時間宣言型で声かけを変える
- 実況型:「お風呂終わったね。次はパジャマに着替えよう」
- 選択型:「先に歯みがきする?それとも明日の準備?」
- 時間宣言型:「あと10分で消灯するよ。時計の針が“9”になったらベッドへ行こう」
「早く!」ではなく行動の見通しを示す言葉に変えることで、子どもは安心して次の行動に移れます。
チェックリストやタイマーで“見える化”する
「やることリスト」を寝室やリビングに貼っておくと、子ども自身で確認できるようになります。
終わったらチェックを入れる仕組みにすれば、親が何度も声をかける必要がなくなります。
またタイマーやアラームを使って「機械に言わせる」ようにすれば、親子のイライラも減ります。
寝室環境を整える
眠りやすい環境づくりも大切です。
部屋の照明は暖色で暗めに、室温は20〜22℃程度、音や光の刺激を減らすことを意識しましょう。
お気に入りのぬいぐるみや安心できる寝具をそろえるのも効果的です。
声かけと仕組みを工夫することで、「親が叱らなくても子どもが動ける環境」に近づけます。
次は、生活リズムが崩れてしまったときに使えるリセット術をご紹介します。
うまくいかない日のリセット術|3日→1週間で戻す

どんなに気をつけていても、学校行事や旅行、夜更かしが続いてリズムが崩れることはあります。
そんなときは「もうダメだ…」と思わずに、リセットの手順を踏めばまた整え直せます。
- 3日間集中:就寝・起床を10〜15分ずつ前倒し
- 1週間固定:毎日同じ順番・同じ合図で習慣化
- 崩れてもOK:「また始めればいい」でリセット可能
3日間集中でまずは30〜45分戻す
生活リズムは一気に変えるのではなく、就寝・起床を10〜15分ずつ前倒ししていきます。
3日間で合計30〜45分戻すのを目安にすれば、子どもも負担なく調整できます。
1週間同じ順番・同じ時間・同じ合図で固定する
リズムを戻すときは、毎日同じ順番・同じ時間・同じ合図を意識すると習慣化が早まります。
「お風呂→歯みがき→絵本→就寝」という流れを守るだけでも、体は自然に眠る準備を始めてくれます。
崩れても大丈夫。「また始めればいい」でOK
完璧に守れなくても心配はいりません。
大切なのは「もう一度やり直せばいい」と考えること。
親がリラックスしていれば、子どもも自然とついてきます。
「リズムは何度でも取り戻せる」と覚えておきましょう。
最後に、今回の記事の内容を振り返りつつ、親御さんへのエールをお伝えします。
まとめ|完璧じゃなくて大丈夫。少しずつで睡眠リズムは整う
小学生の睡眠不足は「成績」「感情」「体調」にも影響する大切な問題ですが、
基本のポイントを押さえれば必ず改善していけます。
- 起床・就寝は10〜15分ずつ前倒しして少しずつ戻す
- 21時以降は画面オフ+夜のルーティンで寝つきを安定させる
- 朝の日光+たんぱく質の朝食で体内時計を整える
チェックリストを活用して「わが子の今の状態」を知り、
原因に合わせた改善方法や声かけを少しずつ取り入れることが大切です。
そして、崩れてしまっても3日〜1週間のリセット術でまた整え直せます。
子どもの睡眠リズムは、親が無理に矯正するものではなく、
一緒に工夫しながら整えていくもの。
「完璧じゃなくても大丈夫。できることから少しずつ」で、親子の毎日をラクにしていきましょう。
関連ページもぜひ参考にしてください。
・朝の支度と忘れ物対策|スムーズに動ける仕組みづくり
・夜更かし対策と睡眠改善|21時以降は画面オフで整える
・小学生の生活習慣が乱れる原因と整え方
この記事を書いた人
さくら|教育系出版社の元編集者/小学生2人(小3・小6)のママ。
子どもの学びや生活習慣に関する記事を中心に、
「ママ目線で共感できる」「すぐに役立つ」情報を発信しています。
自身の子育て経験と編集の視点を活かし、
忙しい親御さんが少しラクになれる工夫をお届けします。
▶ 他の記事は 「小学生の生活習慣まとめ」 からご覧いただけます。



コメントを投稿するにはログインしてください。