朝になると「行きたくない」「体がだるい」と布団から出られない——。
小学生の登校しぶりは、心の弱さではなく生活習慣(睡眠・朝食・休日との時間差)の乱れが関係していることも多いものです。
「このまま不登校になるのでは…」と心配になるかもしれませんが、
まずは小さな整え直しからで大丈夫です。今日からできる工夫で、少しずつ“行ける気持ち”を取り戻せます。
この記事では、最初に改善のための3つの基本を提示し、
そのあとでチェックポイント・原因のしくみ・親の声かけ・相談の目安へと進めていきます。
完璧を目指す必要はありません。
「できる日を重ねていく」ことで、安心して続けられます。
結論|登校しぶりは生活習慣の乱れが引き金になることが多い
登校しぶりの背景には友だち関係や勉強への不安などもありますが、
もっとも取り組みやすく改善につながりやすいのが生活習慣の見直しです。
- 起床・就寝を10分ずつ前倒し × 3日 … 無理なく体内時計を戻す
- 夜9時はデジタル断ち+固定ルーティン … 脳の興奮を下げて自然な眠りへ
- 朝の日光+たんぱく質の朝食 … 体を目覚めさせ、だるさを軽減
この3つの習慣を整えるだけでも、
「だるいから行きたくない」→「少しずつなら動ける」へ変わっていくケースは多くあります。
これがサイン|登校しぶりの見え方と生活習慣が原因かも?のチェック
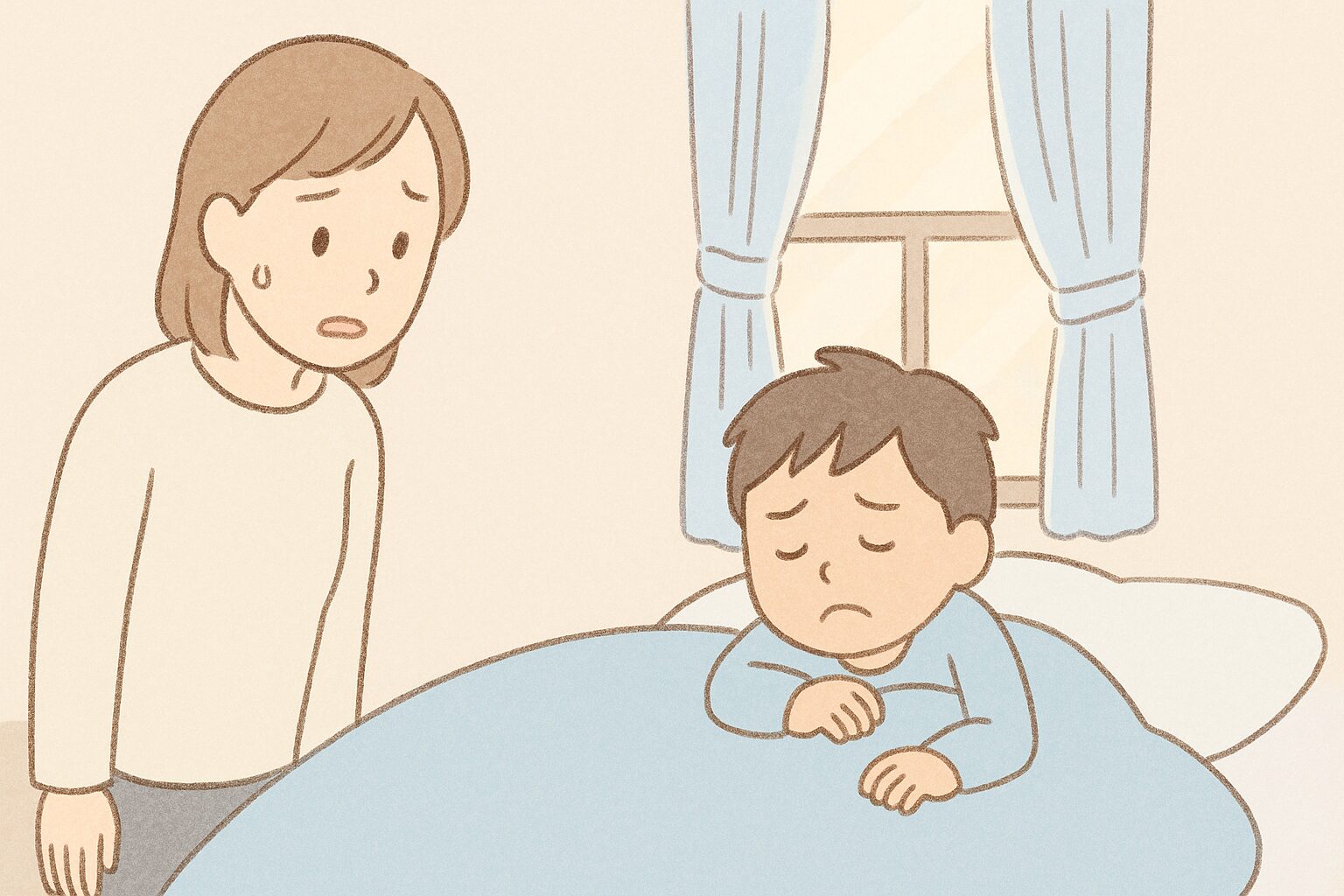
登校しぶりは、ある日突然「学校に行きたくない」と言い出すだけではありません。
生活習慣の乱れが背景にある場合、次のようなサインが見えてきます。
登校しぶりの主なサイン
- 朝なかなか起きられない(布団から出られずぐずぐずする)
- 「学校に行きたくない」と涙や不安を訴える
- 頭痛やお腹の痛みを繰り返す(体調不良を理由に行きたがらない)
- 不機嫌・イライラが朝に強く出る
これらは不登校の前段階として現れることもあるため、早めの気づきが大切です。
ただし「すぐに不登校になる」というわけではなく、
生活習慣を整えることで改善するケースも多いのが特徴です。
生活習慣が原因かチェックしてみよう
- 睡眠時間は9〜10時間とれている?
- 就寝・起床の時間は毎日ほぼ一定?
- 朝ごはんを毎日しっかり食べている?
- 休日と平日の起床・就寝の差が大きすぎない?
これらのチェックに当てはまるものが多い場合、
生活習慣を整えることが登校しぶり改善の第一歩となります。
改善法|状況別に“今すぐやること”を決める

登校しぶりに生活習慣の乱れが関わっている場合、
「どの場面でつまずいているのか」を見極めると対策が立てやすくなります。
ここでは状況別に、すぐ始められるリセット法と声かけの工夫をまとめました。
朝起きられないときは「10分ずつ前倒し×3日」
いきなり大きく時間を変えると失敗しやすいので、
就寝・起床を毎日10分ずつ前倒しして3日で30分戻す方法が現実的です。
朝はカーテンを開けて日光を浴び、朝ごはんでエネルギーを補給しましょう。

声かけ一言:
「今日は7時に起きられたね。次は7時−10分で挑戦しよう」
夜更かしが続くときは「夜9時のデジタル断ち+ルーティン」
スマホやゲームは脳を覚醒させて眠気を妨げます。
夜9時はデジタル断ちを合図にし、
「お風呂 → 歯みがき → 本を読む → 就寝」という流れを固定するのが効果的です。

声かけ一言:
「9時になったら画面おしまい。本を1冊読んでから寝よう」
長期休み明けは「3日間集中リセット」
夏休みや冬休み明けは夜型生活からの切り替えが大変です。
3日間だけ集中してリズムを戻すつもりで、
朝は外に出て朝日を浴び、軽く体を動かすとリセットしやすくなります。

声かけ一言:
「まずは3日間、一緒に朝外に出て深呼吸してみよう」
だるさが残るときは「軽い運動で眠気スイッチ」
朝ごはんを食べても体が重いときは、
5〜10分のストレッチや散歩で体を軽く動かすのがおすすめです。
日中に活動すると夜の眠気が自然に訪れ、翌朝の起床がスムーズになります。

声かけ一言:
「外の空気を吸いに行こう。体を動かすと眠りやすくなるよ」
ポイントは「小さなゴール」を設定すること。
一気に直そうとせず、「10分」「3日間」「まずは夜9時から」など、
続けやすい工夫を積み重ねていきましょう。
改善法|状況別に“今すぐやること”を決める
登校しぶりの背景に生活習慣の乱れがある場合、
「どの状況でつまずいているのか」を見極めて対策を考えると効果的です。
ここでは原因別に、家庭でできる具体的なリセット法をご紹介します。
朝起きられないときは「10分ずつ前倒し×3日」
いきなり1時間早く起きるのは負担が大きすぎます。
毎日10分ずつ起床・就寝を前倒しして、3日で30分戻すスモールステップ法が現実的です。
朝はカーテンを開けて日光を浴び、朝ごはんをしっかり食べることで体内時計をリセットしましょう。
夜更かしが続くときは「21時画面オフ+夜ルーティン」
スマホやゲームを夜遅くまで続けると、脳が興奮して寝つきが悪くなります。
21時以降は画面オフをルールにし、
「お風呂 → 歯みがき → 本を読む → 就寝」という決まった流れを作ると自然に眠りに入りやすくなります。
長期休み明けは「3日間集中リセット」
夏休みや冬休みは、夜型の生活になりがち。
新学期が始まったら、3日間だけ集中して生活リズムを戻すのがおすすめです。
朝は外の空気を吸って軽く体を動かし、朝日と活動でリズムをリセットしましょう。
だるさが残るときは「軽い運動で眠気スイッチ」
朝食を食べてもだるさが残る場合は、
登校前に5〜10分のストレッチや外遊びを取り入れると、夜の眠気が自然にやってきます。
体を動かすことが、次の日の「眠りやすさ」につながります。
無理に一気に直そうとせず、
「10分ずつ」「3日間だけ」「まずは夜ルーティン」のように
小さなゴールを設定するのが続けやすさのポイントです。
『一緒にやろう』に言い換えると動きやすい(親の声かけ・見える化)

登校しぶりがあると、つい「早くしなさい!」「なんで動かないの!」と強い言葉になりがちです。
でも子どもにとってはプレッシャーが増え、さらに動けなくなることも…。
声かけを少し変えるだけで、子どもの反応はぐっと楽になります。
声かけの工夫|実況型・選択型・時間宣言型
- 実況型:「今ランドセルに教科書を入れてるね」「あと水筒を入れたらOKだよ」
- 選択型:「先に顔を洗う?それとも先にごはん食べる?」
- 時間宣言型:「あと5分で出発だから、そろそろ靴下はこうか」
命令ではなくナビゲートするイメージで伝えると、子どもも行動しやすくなります。
チェックリストやタイマーで“見える化”
毎朝「言い続ける」ストレスを減らすには、
チェックリストやタイマーを使って子どもが自分で確認できる仕組みにしましょう。
「できたらシールを貼る」など視覚的な達成感も有効です。
前夜の準備で朝の抵抗を減らす
夜のうちにランドセルや提出物をそろえておくと、
朝のバタバタが減り、登校までの流れがスムーズになります。
「準備を一緒にやろう」と声をかけることで、翌朝のハードルが下がります。
親の「言葉」だけに頼らず、
仕組みと見える化で“自分から動ける朝”を作ることが大切です。
なぜ効く?|登校しぶりと生活習慣の関係
生活習慣の改善が登校しぶりに効くのには、きちんと理由があります。
体内時計とエネルギーのバランスが崩れると、体も心も「学校に行きたくない」というサインを出しやすくなるのです。
- 睡眠不足 → 脳と体の回復が追いつかずだるさ・不安感が増える → 布団から出られない
- 朝食不足 → 血糖値が安定せず不機嫌・集中力低下 → 授業への意欲が下がる
- 休日と平日の時差 → 体内時計が乱れて週明けに強い抵抗感 → 「行きたくない」と感じやすい
つまり、登校しぶりは「心が弱いから」ではなく、
生活リズムの乱れが原因で“行けない状態”になっている場合が多いのです。
だからこそ、生活習慣を整えることが改善の第一歩になります。
改善しない・悪化する時の次の一歩(相談の目安)
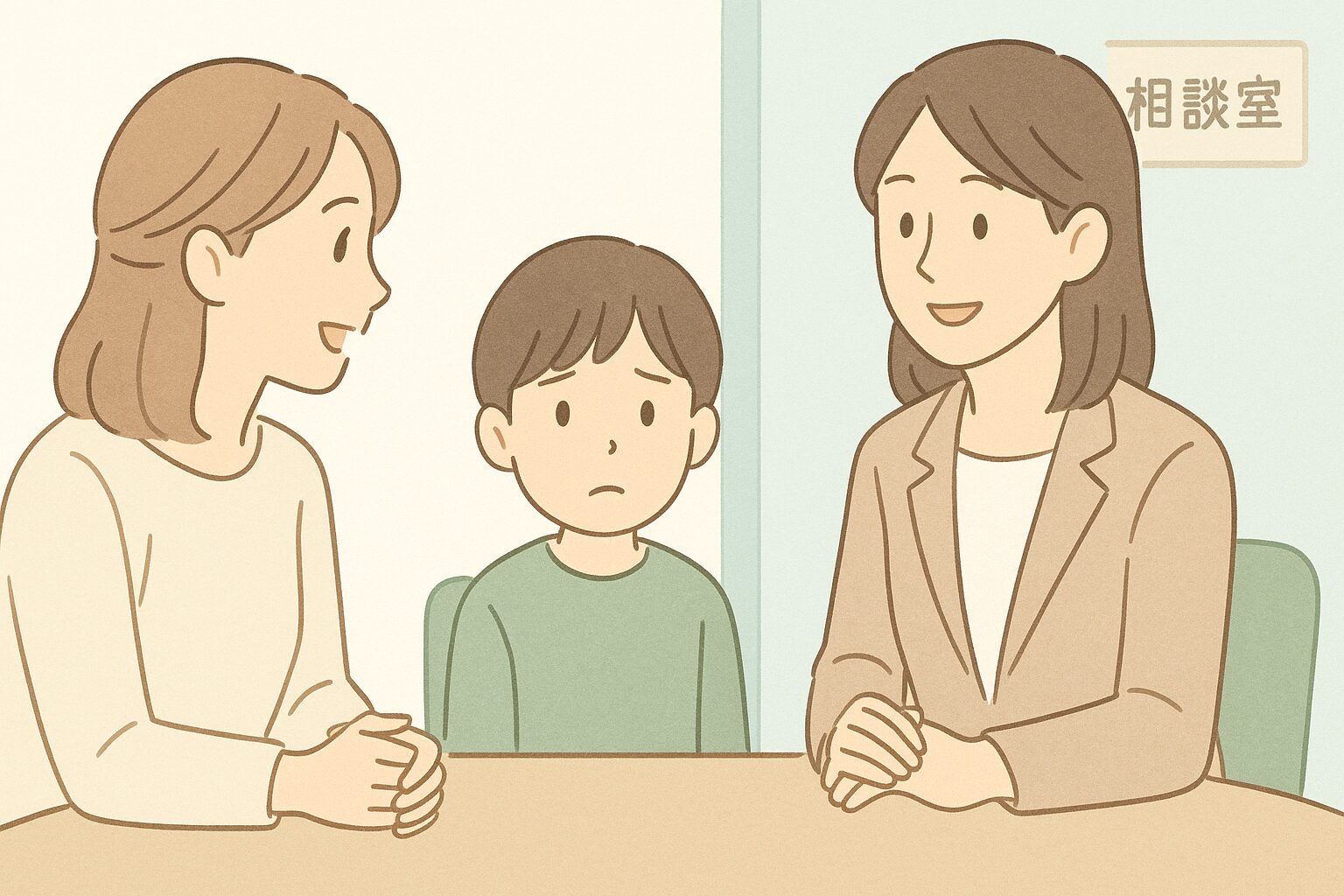
生活習慣を整えても登校しぶりが続くときは、
「もう少し様子を見よう」よりも「早めに相談」が安心につながります。
ここでは、相談すべき目安と活用できる窓口を整理しました。
- 週に2回以上、朝に「頭痛・腹痛・立ち上がれない」が続く
- 2週間以上生活リズムの工夫をしても改善が見られない
- 本人が強い不安や涙を繰り返し訴える
まずは学校に相談
担任の先生や養護教諭に状況を伝えましょう。
「朝起きられない日が続く」「体調不良を頻繁に訴える」など、
具体的な様子をメモして伝えると共有しやすいです。
スクールカウンセラー・教育相談機関を利用
学校に配置されているスクールカウンセラーや、地域の教育相談センターも頼れる窓口です。
第三者に話すことで、親も子も気持ちが軽くなることがあります。
医療機関に相談する目安
「朝になると体が動かない」「頭痛・腹痛が慢性的に続く」など、
身体的な症状が強い場合は小児科や専門外来に相談しましょう。
起立性調節障害や睡眠障害などが隠れているケースもあります。
早めに相談することは「弱さ」ではありません。
子どもの安心と、親の心の余裕を守る大切な行動です。
まとめ|少しずつ整えれば“行ける気持ち”は戻りやすい
登校しぶりは「怠け」ではなく、
生活習慣の乱れが原因で“行けない状態”になっていることも多いものです。
まずは家庭で取り組みやすい工夫から、少しずつ整えていきましょう。
- 10分ずつ前倒しで起床・就寝リズムを戻す
- 夜9時のデジタル断ち+固定ルーティン
- 朝の日光とたんぱく質の朝食
「今日はできなかった」と思う日があっても大丈夫。
また明日から少しずつ取り組めば十分です。
無理に完璧を目指さず、できるところから続けていきましょう。
さらに詳しい工夫やケース別の対応は、以下の記事で紹介しています。
あわせて読むことで、登校しぶりへの理解とサポートの幅が広がります。
登校しぶりは一歩ずつの生活習慣改善で変えていけます。
親子で焦らず、安心して取り組んでいきましょう。
▼ 関連タグからもっと読む
今回の記事では「登校しぶりと生活習慣」をテーマに取り上げました。
同じお悩みに役立つ記事を、以下のタグから探せます。



コメントを投稿するにはログインしてください。